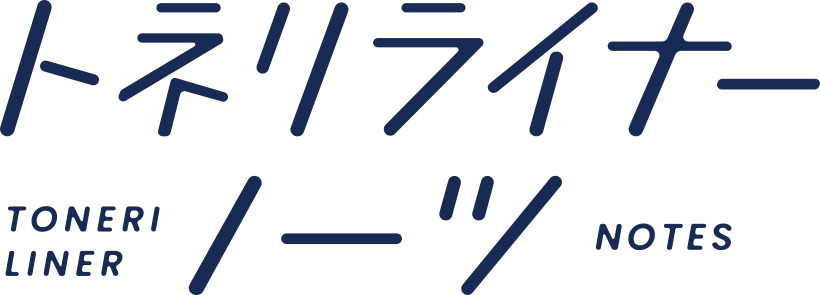足立区を拠点とする子どもの理科実験・ワークショップの教室「わんだーラボラトリー」を主催する和田由紀子さん(ゆっきぃ先生)は、足立区の学校支援員として様々な子どもたちを支援しています。

そんな“ゆっきぃ先生”が、個性あふれるユニークな子どもたちの物語を綴るのが、「子どものすることには“ワケ”がある」です。第5話は、ゆっきぃ先生と考える「“怒り”に効くおまじない」をお届けします。
「怒り」をどう消化するか
こんにちは、あるいは、はじめまして。「わんだーラボラトリー」主催の和田由紀子です。
みなさんは、はらわたが煮えくり返るほどの「怒り」が沸いてきた時、どのように対処していますか? 小さな子どもたちは、とっさにこんな風になることがあります。「シネ!キエロ!ゴミ!カス!バカ!」などと、叫ぶ…。相手を、叩く、蹴る、ひっかく、噛む…。周りのものを、投げ飛ばす、蹴り飛ばす、踏みつける、壊れるまで叩いたり蹴ったりする…。これらの行動は、周囲の人を驚かせたり、傷つけたり、物の破損につながったりするので、必ず止めて、落ち着くまで寄り添います。
また、こんな子もいます。泣く、固まる、走って逃げる、隠れる…。こちらは、なだめるというか、始めから気持ちに寄り添うことが多いです。これらのとっさの行動は、その時に無意識で行われていることが多いので、どんなに言い聞かせても、その子が後から反省して相手に謝ったり壊したものを片づけたりしても、簡単には変わりません。押さえ切れずに溢れてくる感情をなんとかしたくて、小さな体で必死に対応しているからです。

大人はどうでしょうか?大人は、滅多なことでは大声で叫びませんし、泣きもしません。燃え上がるほどの怒りで心の中がどんなに苦しくても、たいていの場合はぐっと堪えて、冷静になろうと理性を働かせ、その場にふさわしい行動を考えるのではないでしょうか?
それは、おそらく、この社会で生きていくために必要なスキルです。子ども達も年齢が上がるにつれて、暴言に頼らずに相手の間違いを指摘することを覚え、激情を暴力に変換せずにやりすごす術を身に着け、泣かずに自分の気持ちを言語化することを学びます。
もちろん、完璧にできることはない(大人もできない)ですが、そう振る舞うことがよしとされていることを認識します。そして、少しずつ、自分の中に湧き上がる「怒り」と、うまく付き合えるようになっていくのです。

「怒り」という感情は、その下に期待・悲しさ・寂しさ・恥ずかしさ・不安・恐れなどの気持ちが隠れていると言われます。期待通りにならなかった、思ってもみないことを言われて悲しかった、いきなり決めつけられて不安だった…などなど。
私はもういい大人なので、その場の「怒り」に動じることはあまりありません。自分の「怒り」と何度も向き合っているとパターンを感じて、「あぁ、またそのパターンで怒っているのね」と自分に呆れることの方が多くなるのです。だから、その場で怒りを静めるのは速い。
けれども、その場では収めていても、グズグズと引きずる「怒り」の対応にはいつも困っています。もう終わったことなのに、いつまでも恨みがましく、心の中で燻っている「怒り」の感情。何時間も、何日も、時には何ヶ月も、何年も。
子どもたちは、「怒り」をすぐに忘れてしまうことが多いようですが、時々思い出したように、以前の出来事に対して突然怒り出す子がいて、私は親近感を持ちます。そして、そういう時は、とっておきの“気休め”を伝えるようにしています。
「怒り」には小さな気休めを
のあくん(仮)は、時々、火が付いたように怒り出す。それは、いつも突然で、周りにいる人は毎回驚かされる。あっ!と気が付いたときには、机の上にあったものを手あたり次第で床に投げ落としたり、上履きを蹴り上げて天井にぶつけたり、壁に貼ってあった掲示物をビリビリに破いたりする。「シネ!」「ふざけんな!」「消えろ!」などと叫んでいることも多いのだが、それがいったい何に対してなのかは、あまり良く分からない。
よく見ていると、毎回キッカケとなるようなことはあって、例えば「100点の自信があったテストが90点だった」とか「給食をもらうのに並んでいたら横入りされた」とか「タブレットを使える時間が思ったよりも短かった」とか、確かに誰にとっても少しばかり心が乱されるようなことが、それらの行動の前にはある。けれども、そんなに怒るようなことだろうか?と、疑問に思う。些細なことで怒り狂うものだから、彼の周りにいる人々は、ビクビクしている。どこに地雷が埋まっているか分からないし、その怒りが自分に向いた時のダメージが大きいからだ。

しかし、怒っている時ののあくんは、それはそれは辛そうで、たいていは泣き叫んでいる。声をかけても簡単に静まることはなく、差し出した手は即座に振り払われる。どうしてそんなに怒りが持続するのだろう?と、いつも驚いてしまう。
そのうちに、その怒りは、その時の怒りだけではないようだ、と分かってきた。テストがうまくいかなかった時は以前のテストでミスしたことにも怒りが及んでいるし、横入りされた時はそのことだけでなくて今までにその子にされた嫌なこと全部に対して怒っている。タブレットをもっと使いたかった気持ちは、昨日のことも1週間前のことも1ヶ月前のことも、全ての記憶を注ぎ込んで怒っている。
どんなに怒っていても、普通は時間が経つとおおむねリセットされると思うのだけど、彼はそうではないらしい。怒りが積み上がって重なり合って常に心の中で渦巻いているために、ほんの些細なことで爆発してしまうようなのだ。怒りを積み上がらせない方法はないだろうかと考えて、あの手この手でなだめすかし、話をし、彼が少し落ち着いた頃に、私は小さな気休めを口にする。

「100点取るために真剣に頑張ったのあくんに、この後何か素敵なことが起こりますように」
「横入りしてくる人には、じゃんけんで負け続ける呪い、か、何もないところで躓く呪い、をかけましょう」
「タブレットが少ししかできなかった代わりに、今日のおやつに好きなものが出ますように」
これらは、本当に小さな気休めだ。でも、怒りをその場に留め置かずに、視点を未来に向けるには、ちょっぴりイイ方法かな、と思っている。
世の中、良いことと悪いことはセットだ。悪いことばかりは続かない。嫌なことを引き受ける代わりに、良いこともきっとある。「素敵なことって何?」 とか「おやつ、何かなあ」 とか、ほんの少しそちらに興味が動くと、張りつめていた心に隙間ができる。心は緩むと、正常に働くことが多い。

もちろん、横入りみたいな嫌なことをされたら、その相手とその場で解決するのが一番だろう。でも、それが思ったようにうまくいかないこともある。そういう時は、心の中でこっそり小さなイタズラを考えるのだ。そして、実際にそうなった相手を想像して、ニヤリとする。そのくらいは、いつだって許される。
「あいつ、一生じゃんけんで負ければいいよね!」 と言い募るのあくんに、「そうだねえ。一生、は、難しいかもしれないけど、1週間でも負け続けたらへこむよね」などと答えてみる。
無理難題を押し付けてくる相手に、「静かな会議の真っ最中にお腹の音が響く呪い」をかけるというのは、今でも私が頭にきたときに使うやり方で、その手で怒りをためずにやり過ごせているのだと思っている。
わんだーラボラトリー

文=和田由紀子さん
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/yukki/
イラスト=堀井明日美さん