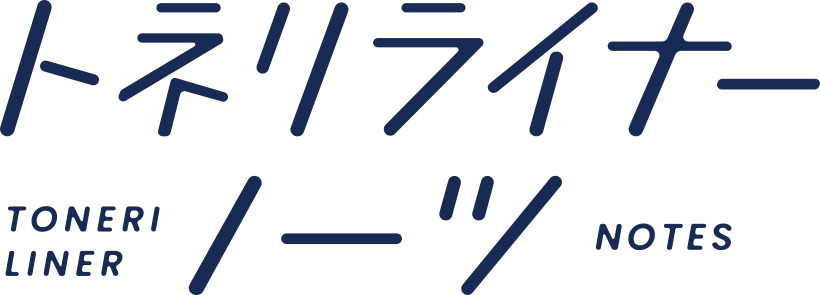足立区綾瀬にある「Haleハレノヒ訪問看護ステーション」では、子どもの居場所支援をする「ハレノヒのお部屋」や「ハレノヒおとなこども食堂」を開催しています。訪問看護と子どもの居場所支援が連携する意味について、「Haleハレノヒ訪問看護ステーション」代表の鈴木沙恵子さんに取材しました。取材者は、元看護師でライターの佐藤みなさんです。
※この記事は、2025年7月8日にnoteでアップされた『「できない」が「できる」に変わる!発達に偏りがある子どもの訪問看護と不登校支援|インタビュー』を、トネリライナーノーツ編集部が再編集・写真を撮影(2025年7月)しました。

足立区綾瀬にある「Haleハレノヒ訪問看護ステーション」には、成人・小児をあわせて200人以上の利用者がいます。子どもの居場所支援やこども食堂も同時に運営しており、とくに、発達に偏りがある子どもへの支援に力を入れています。
代表を務める鈴木沙恵子さんは、不登校に悩む親子を支えたいと、子どもの居場所支援ができる場所「ハレノヒのお部屋」を作りました。子どもたちに深い愛情を注ぎ、「あなたはできるようになる」と伝え続ける鈴木さん。訪問看護と子どもの居場所支援が連携する意味について、お話を伺いました。
医療者だからこそできる支援

「ハレノヒのお部屋」はマンションの一室にあり、明るく広々とした場所です。和室やぬいぐるみのある部屋、スタッフルーム(職員室)、バランスボールやテレビが置かれている部屋など、さまざまな空間が用意されています。
そこで子どもたちは、勉強したり体を動かしたりして過ごします。憂鬱な日は寝転んでいても大丈夫。ハレノヒのお部屋に通うこと自体が、子どもたちの一歩だからです。もちろん、自由に過ごすだけではなくルールにのっとって行動できるよう、時間ごとに過ごし方を決め、適応力を伸ばしています。

「訪問による個別療育では、自分が信頼している大人と話しているので会話に困りません。でも、小集団になると難しいんです。発達に偏りのある子どもは、集団の中で戸惑ったり適応できなかったりします。だからこそ、ハレノヒのお部屋では集団での成功体験が積めるようにしています」
大切なのは、子どもが小集団の中でも過ごせると実感できること。そのために、円卓で作業して友だちの存在を意識できるようにしたり、イベントで役割を任せて責任感を持てるようにしたりしています。子どもたちは少しずつ自信を育んでいくのです。このような関わりは、鈴木さんが身につけてきた知識と経験に基づいています。

「発達に偏りのある子どもが小学校・中学校に適応できないのには、理由があります。本来は成長とともに消失するはずの原始反射が残っていると、姿勢の保持ができなかったり不安や緊張が増して苦しくなったりするんです。子どもは学習に取り組む以前に、指示に従うことで精一杯。私たちは本人と親御さんにそれを理解してもらえるよう、個別に面談し、『困っている理由は必ず改善できますよ』と伝えています」
自分の身長ほどもありそうな長くやわらかなポールを持ち、走ったりぐるぐる回ったりしている子どもたち。鈴木さんはみんなに優しく声をかけ、表情を確かめながら一緒に体を動かしていました。
訪問看護と子どもの居場所支援の両立

鈴木さんは、訪問看護師として15年のキャリアを持ち、訪問療育にも関わってきました。療育指導について勉強し、自閉症タッチセラピスト、障害コミュニケーション指導者、プロビジョントレーナーの資格も取得しました。
10年かけて指導・管理ができるほどに学びを深め、訪問看護ステーションの立ち上げを決意します。その際は、「必ず子どもの居場所支援をやろう」と心に決めていたそうです。

「訪問の自閉症療育により、子どもの行動が変わります。それでも、フリースクールや区が行う不登校支援学級に行くことを拒否してしまう子どもはたくさんいます。そのような子どもたちには、通いやすい小集団の環境で、発達の偏りを改善するトレーニングがまだまだ必要なんです。だから、私は無料で気軽に利用でき、医療的な視点でサポートできる場所を作ろうと思いました」
そのような思いに至ったのには、鈴木さん自身の過去が関係しています。鈴木さんの子どもたちは新しい環境に馴染むことが難しく、学校に通えない時期がありました。「子どもが自分らしく過ごせて成功体験を積めるような場所が、身近にはない」と感じていたそうです。
子どもは不登校中に、感覚の過敏さが悪化したり、できていたことができなくなっていき混乱したりします。そして、家族に感情を爆発させてしまうのです。

「私は保護者として、つらい思いをたくさん経験しました。だからこそ、不登校の子を持つ家族には、苦しみを抱え込んでほしくありません。地域の中で医療者へ相談できる場所があれば、専門的な視点による発達状況の評価が可能です。そこから訪問看護につなげることで、不登校の初期から支援ができるんです」
鈴木さんは、2023年11月にハレノヒ訪問看護ステーションを設立します。そして半年後の2024年4月、「ハレノヒのお部屋」と「ハレノヒおとなこども食堂」を開始しました。
訪問看護から次のステップへ

訪問看護では、不登校の子どもに対して、医師の指示のもと必要な療育を行います。まずは子どもの発達状況を評価し、運動や学習などの支援を実践していくのです。「ハレノヒ訪問看護ステーション」では、看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが連携して子どもたちを支えています。
「子どもの発達に偏りがある場合、『できない』には根拠があります。たとえば、挨拶をしない子どもは、相手の目を見て会釈することが困難です。注意を向けたものに対して視線を保ち続けるのが難しい。また、適切な行動の正解を脳が理解できていないこともあるんです。私たちは、ビジョントレーニングやコミュニケーションの練習をして、共感力が育めるよう支援しています。本人の態度や家庭でのしつけが問題なのではありません。未発達な部分があるために反応できないだけなんです」。

不登校になった子どもにも、保育園や幼稚園ではできていたことが数多くありました。しかし、小学校という新しい環境や集団生活の中で感覚過敏や学習障害などの特性が目立つようになり、学校生活がつらくなってしまうのです。
そのような状況でも、専門的な知識に基づき適切にトレーニングすれば、子どもの「できない」は「できる」に変化します。鈴木さんは「子どもには十分な力があるので、目標は、本来の自分を取り戻すこと。自分は何が苦手でこんなにも大変な思いをしているのか、自分自身を理解してもらう」と話します。

訪問看護によるトレーニングと「ほら、できるでしょ」の声かけは、子どもに自信を与え、意識を外に向けることも可能にします。行動が変化すると、友だちの必要性に気づくようになるのです。ハレノヒのお部屋は、子どもが無理なくステップアップできる場所となっています。
本人が行きたいと感じれば、子どもは外に出ます。しかし、通所を継続するためには、楽しさと安心を感じられる場所であることが必要です。
「ハレノヒのお部屋では、子どもの気持ちを最優先しています。違う部屋に行きたくなる気持ちや、暴言を吐いてしまうことへの理解があるからです。みんなは、苦しくなったときに先生がすべて理解してくれることを知っているんです」
訪問によって生まれた信頼関係が、次のステップに進む子どもの成長を助けています。
頼ることから始めてほしい

「ハレノヒのお部屋」に通所できるようになった時点で、子どもの行動や意識は大きく変化しています。通うことが楽しくなり、子どもたちの暴言や争いはなくなっていくそうです。
「何年も不登校だった子どもがハレノヒのお部屋に来るようになり、通所できなくなったケースは今までありません」、鈴木さんは言います。偏った発達のバランスを整えていけば、1時間集中して勉強できるようになり、学校やフリースクールにも通えるようになります。
そのように子どもが変化するには、本人の努力や支援者の関わりだけでなく、一番近くにいる家族の存在が重要です。子どもの現状や課題、そして対応の仕方を家族に伝えています。
ときには、「ハレノヒのお部屋」での写真を見せて、子どもが頑張っている姿を示すこともあるそうです。ハレノヒ訪問看護ステーションは、家族があきらめずに一緒に頑張れるよう、24時間対応で親子を支えています。

「ずっと頑張ってきた親御さんの心は、子どもと同じように傷ついているんです。だから、行動や気持ちに寄り添い、親子が苦しくならない方法を見つけられるよう支援しています」
このようなサポートは、支援の手を求めてくれた人にしか届けられません。だからこそ鈴木さんは、「不登校になった初期から地域を頼ってほしい」と話します。子どもの不登校が長引くほど、他人が家に入るのは難しくなっていくのです。
「発達に偏りのある子どもは、学校に行くことに対して心と体がバラバラになっていると表出しています。一方、家族は、愛情から『学校に行けるようになってほしい』と願っています。しかし、この思いのズレが苦しみを生んでしまう。地域には無料で利用できる施設があり、支えたいと思っている人がたくさんいます。それは、医療者だけじゃありません。子どもが家族としか喋れなくなる前に、家族以外の人にサポートしてもらうことを始めてほしいんです」
鈴木さんの言葉には、同じ道を歩んだ人が持つ共感と優しさ、そして苦しむ人への愛がありました。一人で抱えなくていい、支えてくれる人が待っています。
ハレノヒのお部屋・ハレノヒおとなこども食堂
ホームページ
https://harenohi-shokudo.com/
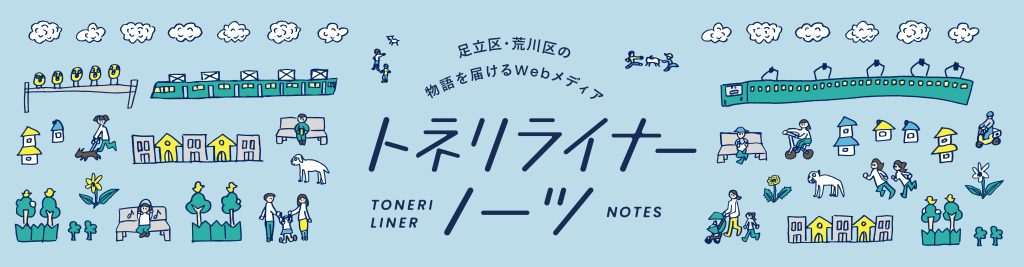
取材=佐藤みな
https://note.com/minya22
撮影=山本陸(トネリライナーノーツ カメラマン)
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/riku/