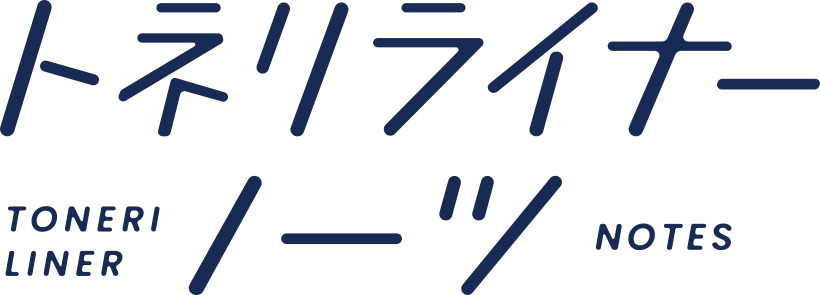地域のユース世代を応援する団体や個人にフォーカスを当てて、それぞれの活動への想いや課題などを取材することによって、輪を広げていく連載が「ユースサポーターの輪」です。ユース世代とサポート側の繋がり、サポート側同士の繋がり、活動を応援する人たちとの繋がり。それぞれの繋がりが輪となり広がることで、さらなる応援を呼ぶことを目指します。

#5では、足立区の学校支援員で、子どもの理科実験・ワークショップの教室「わんだーラボラトリー」主催もしている“ゆっきぃ先生”こと、和田由紀子さんにお話を伺いました。聞き手は、トネリライナーノーツ編集者で「らんたん亭」メンバーのしまいしほみが務めます。
(取材日:2025年4月21日)
和田由紀子さんのプロフィール

- 学校支援員
- 「わんだーラボラトリー」主催
- 公認心理師
元小学校教員。現在は足立区の学校支援員として、発達にデコボコのある子どもを対象に、通常学級での活動をサポート。障がいの有無にかかわらず、子ども一人ひとりに寄り添う支援を行っている。体験を通じて子どもたちの言葉の理解や「失敗を恐れない姿勢」を育む場づくりにも取り組む。
同時に、足立区を拠点とする子どもの理科実験・ワークショップの教室「わんだーラボラトリー」を主催。「ワクワクする体験や失敗してもやり直せる環境が、子どもの発達に深く関わっている」と考えのもと活動中。
子どもの“つまずき”に気づく「学校支援員」の役割

――和田さんはどんな活動をされているか教えてください。
和田さん もともとは埼玉県の小学校の教員でした。足立区に引っ越すタイミングで子育てなどもあり、教員は退職して今は足立区の「学校支援員」という仕事をしています。
学校支援員は、教室に入りづらかったり、教室にいるけれど勉強が難しい子どもたちをサポートする仕事です。
もうひとつの活動は、理科の教員免許を持ってるので、足立区を中心に「わんだーラボラトリー」という出張サイエンスクラスを開催しています。

――学校支援員って、私が小学生の頃はあまり聞かなかったように思うんですが、いつ頃から増えてきたんですか?
和田さん おそらく、昔は学校支援員はいなかったと思います。少なくとも、私が小学生の時は、車椅子でないと学校に来られないとか、水を飲む時に必ず吸引や胆の処理が必要というような医療的なサポートやケアをする方はいましたが、それ以外の方は見たことがなかったですね。私が教員になった20年前くらいに少しずつ出てきて、ここ10年ぐらいで急増しているように感じます。
――必要性が高まってるということですか?
和田さん そうですね。子どもの数は減っているけれども、通常の学校の枠では収まりきれないタイプの子たちがたくさん出ているからという感じがします。

――子どもたちをサポートする方には、どんな方がいらっしゃるんですか?
和田さん 私がやっている学校支援員は、週に複数の学校を訪れて、それぞれ特定の子どもを担当します。現場では、対象の子どもを観察し、関わり方を考え、実際に関わってみます。そして、スーパーバイザーの助言をもらい、また接してみて、「この子には、こういう風な関わり方がいいんじゃないでしょうか」と学校に具体的な支援の提案をしています。
他にも、学習支援員、介助員(スクールアシスタント)、登校サポーターという方などがいて、さまざまな場面で子どもたちをサポートしていますよ。
――学校にはいろんな人が携わってるんですね。
中学生の心の扉を開けるには――

――中学校にも学校支援員さんはいらっしゃるんですか?
和田さん 中学校にもいますよ。私も来週は中学校に行きます。
――中学校にも行ってらっしゃるとは知らなかったです。小学生と中学生だと関わり方も違いそうですが、そのあたりどうでしょう?
和田さん そうですね。小学校低学年の子どもたちは、教室から出てしまったり、泣いてどうしようもなかったり、固まってしまったりすることがあります。そういう子には、教室の中でどう過ごすか、生活のルーティーンのような基本的なことを一緒にやりながら伝えていきます。
一方で、小学校高学年から中学生になると、「やらなきゃいけないことは分かってるけど、できない」という状態の子が増えていきます。なので、私たちは彼らの“心理的な溝”を埋める役割が大きくなっていきます。

和田さん 例えば、先生が求めることに対して、やらなきゃいけないことを彼らはちゃんと理解してるんです。だけど、できない。うまくいかないんですよね。だから、そこの溝を埋めるように私たちは「先生はこう思ってるんだと思うよ、だからこういう風に言ったらどうかな?」と子どもたちに伝えます。
また、先生の方には「彼なりに一生懸命やっているけれど、ここがとても難しい部分なんです。ハードルを少し下げてあげると、本人も取り組みやすくなると思います」とお伝えします。
――先生たちへの伝え方も大事なんですね。
和田さん そうなんです。中学生にももちろん直接話しますが、先生側に働きかけることも多いです。「この子はこういう子で、ここが苦手で、こういう状況になっています」と、中学校なら各教科担当の先生にそれぞれお伝えすることで、「じゃあ、この教科では、どうしようか?」と具体的なお話ができるようになります。

――中学生は思春期に入って難しい部分もあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか?
和田さん 最初に「困ってることはない?あったら言ってね」と伝えても、思春期に入った中学生は大抵「大丈夫です」と言いますよね。「別に」のように(笑)自分ができないところを話すのは嫌ですもんね。見ず知らずの人に話しかけられて「なんだこいつ」というような反応です。
でも、例えば消しゴムを貸すとか、日常の中の小さな関わりを積み重ねることで、「この人もしかするとちょっと困ってる時呼んだら自分が楽になるかも」と思ってもらえたら、中学生に対する仕事はおしまいです。そうなれば、こちらから無理に踏み込まなくても、向こうから声をかけてくれるようになります。それまでのプロセスが、私の仕事の9割だと思っています。
――ちょっとでも心の扉が開けることが1番の目的なんですね。
やりがいと難しさ、子どもをサポートする“押し引き”のバランス

――学校支援員のおもしろさってどういうところですか?
和田さん おもしろいのは、「できなかったことができた!」という瞬間ですね。
私は小学校3、4年生くらいが1番好きなんですけど、縄跳びとか漢字練習を一緒にやってみた時に、今までのやり方ではうまくいかなかったけど、私が提案してみたやり方がマッチしてうまくいったら「できた!」と嬉しそうな表現をしてくれる瞬間が好きでおもしろいなと思いますね。
中学生だと、時間はかかるんですけど関係が深まって、困った時に「先生来て!」と呼んでもらえた時が1番うれしいですね。そこまで行くのが大変なんですけどね。

――それ、分かります。私は中高生が放課後に来るユースセンターでユースワーカーとして活動しているんですけど、反抗期な中学生がちょっと喋ってくれたときや、こちらからの声掛けに少し笑ってくれたときは本当に嬉しいです。
例えそれが「これ使えますか?」くらいのどうってことない質問だったとしても嬉しくなって「使えるよ、何か作るの?手伝う?」とグイグイ行きたくなります(笑)
和田さん 引き際もすごく考えますよね。もうちょっと行きたいけど、行きすぎたらダメだよねと自分の中で駆け引きしますよね。
――逆に、難しい所はどういうところですか?
和田さん 難しいことは、「本当に困っていることが何なのか、すぐには分からない」という時ですね。書字が難しい子に関わることが多いんですが、「書けるけど、読めない」子たちがいるんです。

和田さん 教科書や板書を見ながらノートに写すことはできるんです。でも、それを読んで理解する事が難しいので、自分ひとりでプリントの課題に取り組もうとすると困ってしまうんです。
けれど、周囲には「写せているから、できている」ように見えるんです。だけど、その子は書けてはいるけれど読めてはいないので、「1人だとできない、困っている」という事に、周囲も、時には本人も、気が付くのにすごく時間がかかるんです。
本人も隠して「できている風」に見せるので余計分かりにくいですしね。「ここがわからないんだ」と気付くまでに時間がかかってしまって、余計な回りくどいサポートをたくさんやってしまうこともあります。
だから、私たち学校支援員は子どもたちをよく観察して、「ここはできるけど、ここはできない」ということにいち早く気づき、彼の特性にあったサポートをするというところが1番難しいですね。
――先生たちは授業をしながら大勢を見るのでなかなか個人の細かいところを見るのは難しいですもんね。
“好奇心”をくすぐる「わんだーラボラトリー」での工夫

――「わんだーラボラトリー」に来る子たちはどういう子が多いんですか?
和田さん 理科好き、興味があると言ってくる小学生が多いです。理科の中でも実験のような動きのあることがおもしろいんだろうなと思っています。
理科のおもしろさは、“情報の結びつき”だと私は思ってるんですけど、子どもたちにとってはそこがおもしろいとは限らないようですね。ペットボトルを飛ばすとか、色水の実験で水の色が変わるとか、しゅわしゅわと泡が出るとか、そのような事が楽しみで来ているように思います。
実験では「あれ?なんで!?」と興味を示す反応をする事が多いので、そこを狙って、「最初にまずは予想を立てなさい」と伝え、予想が結果とどう違うかを考えさせます。そこから、「わかった!」となったあと、他の子が「なんで!?」となった時にどうやって説明するかを考えさせるということを繰り返してるんです。

和田さん 小学3年生ぐらいから来てる子は5年生くらいになると、それが結構できるようになってるんです。私が説明するより、子どもが子どもに説明した方が圧倒的に頭に入るので、そこまでできたらいいなと思いますね。
――小学生から「こういう実験をやってみたい」という要望はあるんですか?
和田さん ありますよ。例えば、水のろ過をやってみたいって言われたことがあって、キャンプ系youtuberさんの動画を見たようで「泥水から飲み水を作りたい」と言われました。
ろ過実験をやるのは良いんだけど、綺麗な水を作るためにいい感じの泥水を作ることが1番難しかったですね(笑)要望があれば、夏休みの自由研究として取り入れたり、連続で来ている子たちだったら「来年やってみよう」と計画したり柔軟に組み込んでます。
――なるほど。小学生からやってみたい事が出てくるのが素敵だし、案を取り入れてもらえるのも小学生にとっては嬉しいことでしょうね。
自由な感性をもつ子どもたちと“細く長く”の関わりを

――和田さんは、小学生と関わることが多いと思いますが、和田さんにとって小学生はどういう存在ですか?
例えば、私がユースワーカーとして中高生と関わる時に思うことが、中高生はいい意味で“宇宙人っぽい”印象があるんですよね(笑)予測不能な行動をする感じだったり、急に叫んでみたり、小さい椅子に縮こまって変な体勢で座ってみたり。
情緒に波があってちょっとしたことで喜怒哀楽がコロコロ変わるところにもすごく愛らしさもあるんですよね。自分も同じような経験をしていたはずなんですが、大人になると忘れてしまっていて不思議な生物に感じるんです。

和田さん なるほど。今おっしゃったような“変な行動”って小学生にはもっとたくさんあるんですよね。すごくたくさん石を集めて並べたり、棒をひたすら振り回したり、どんぐりを集めてたけどいらなくなったであろうから捨てると泣いたり、お水をずっと触ってたりと、本当に意味わかんないことをしてるんですが、そこには何かしらの意味と理由があるんですよね。
彼らはそれをやることによって何か得るものがあるんだと思うんです。その上で、私は彼らの行動を予測したりそういう様子を観察することがおもしろいと感じますね。「この子はこの次にどうするのかな?もしこういう理由だったら恐らくこうなるのかな」と見立てながら観察して、その通りになったら「ああ、やっぱり!」とおもしろくなります(笑)
そのような子どもの衝動、好奇心、感情表現、行動の自由さなどが特に出てくるのが、小学2、3、4年生ぐらいなんですよね。小学5年生ぐらいになると少し客観性が育まれて周りを気にして抑えめになり、その下の学年だとまだ言語化が難しくわからない部分があるんですけど、小学2、3、4年生くらいは全開なので、そのあたりの学年と関わるのは本当におもしろいです。
――予測不能な行動にもちゃんと意味があるんですね。これからも変な行動を見守っていきます。

――今後どういう風に子どもたちと関わっていきたいですか?
和田さん 学校支援員も「わんだーラボラトリー」も単発で関わり後腐れなく終わることが多い仕事なんですけど、それでも最近は「できるだけ細く長く繋がっていたいな」と思うようになりました。
昔、小学校の担任をしていた頃は、卒業する子たちに「先生たちのことはもう1ミリも思い出さなくていいから、君たちは次に行きな」と送り出していたんです。でも、今はちょっと歳を取ったからかなとも思うんですが「心のどこかに残ってたらいいな」と思うんですよね。
だから、学校支援員の方では「今度は別の先生があなたの学校に行くから、その先生ともお話してみてよ。後で、その先生からあなたの様子が聞けたら嬉しいから」と伝えてみたりしています。
「わんだーラボラトリー」の方でも、「いつでも単発で来ていいよ」と伝えています。以前は、1回限りの出会いに全力で向き合ってスパっと終わる関わり方をずっとやってきたんですけど、「人間関係って持続してた方がいいかもと」と思うようになり、少しでも繋がっていられる、心に残っていられる関係性がいいのかなと思ってきたんですよね。

――なんで考えが変わってきたんですか?
和田さん 1回だけではどうしても伝えきれないことがあるから、少しでも“伴走”していける関係が大切だなと思うようになったんです。子どもたちには「見ててよ、私だって失敗するよ。歳だってとるしさ」と、私自身の変化や失敗をみてもらうことで「大人だってそうなんだ」とか「間違えても大丈夫なんだ」などと何か伝わるんじゃないかなという気がしてるんですよね。
――大切ですね。今日はありがとうございました。

『子どものすることには“ワケ”がある』
https://tonerilinernotes.com/category/article/free/yukki-kodomo/
わんだーラボラトリー

取材・編集=しまいしほみ(トネリライナーノーツ 編集者)
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/shimai/
撮影=山本陸
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/riku/