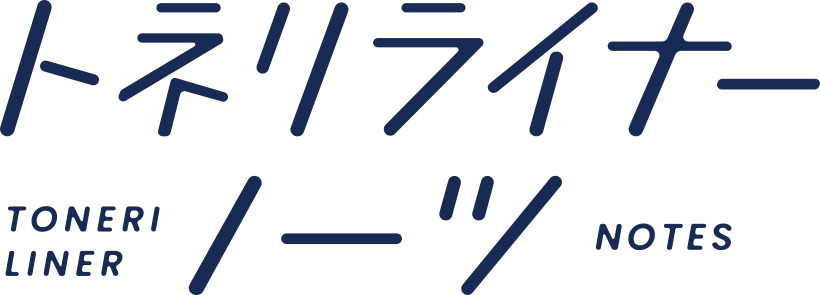「トネリライナーノーツ」が毎月第3日曜に足立区千住旭町にある古民家カフェ「路地裏寺子屋rojicoya」で主催していたイベント「オオシマナイト」で実施する公開取材が、「ガチアダチ サミット」です。

「ガチアダチ サミット」のepisode.8となる今回は、足立区を拠点に活動する特定非営利活動法人「Chance For All(CFA)」グループ事業マネージャーの廣瀬陽香さんに登壇していただいて、「学生たちとつくる子どもたちの未来、CFAが突き進む道」をテーマにお話を伺いました。聞き手は、トネリライナーノーツ編集長の大島俊映が務めます。
(取材日:2025年2月16日)
「CFA」の確固たるビジョン

――はるちゃん、自己紹介と「Chance For All」について教えてください。
廣瀬さん 特定非営利活動法人「Chance For All」でグループ事業マネージャーをしている廣瀬陽香です。「Chance For All」略して「CFA」は、足立区と墨田区で活動している団体で、子どもたちの居場所や遊び場をつくっていて、「生まれ育った家庭や環境に関わらず、誰もが幸せに生きていける社会」を目指しています。
なぜかというと、貧困な子どもたちがたくさんいるという課題もあるんですが、それだけじゃなくて、お金がある子たちの自殺率も実はすごく高いんです。理由として、子どもの自己肯定感が低かったり自分はいる意味がないと思っていたりする子たちが多いということがあげられます。
「生まれ育った家庭や環境に関わらず、誰もが幸せに生きていける社会」という私たちのビジョンはそういう背景からで、実現するために様々な事業を行っています。

――具体的にどんな事業をやってるのか教えてもらっていいですか?
廣瀬さん 「CFA」ができて11年目を迎えるんですが、設立当初から行っているのは学童保育事業です。足立区に6校舎、墨田区に2校舎あって、子どもたちのためを考えた学童保育ということで、日常はもちろん、イベントなども開催して、子どもたちがいかに主体的で“ごちゃ混ぜ”に過ごせるかを大切にしながら運営をしています。
また、私が担当している事業でいうと、「CFA」の学生チーム(大学生主体)が企画・運営を担当している足立区関原の商店街にある駄菓子屋「irodori」があります。1番の目的は駄菓子の販売ではなくて、商店街にいる地域の人たちが子どもたちに声をかけるキッカケを作りたいという想いがあります。
駄菓子屋「irodori」の奥にはフリースペースがあり、そこには大きな黒板や机、ヨギボーなどを置いていて、子どもたちがだらんと過ごせて、“居るだけでいい場所”をつくることを大切にしています。子どもたちは勉強をする子、ゲームをする子、恋バナをする子もいれば、先生の愚痴を言いに「ねえ、ちょっと聞いてよ」と言って学生たちに声をかける子もいます。 駄菓子屋「irodori」は学校でも家でもない、子どもたちが自分で選択できる居場所の1つとなるように運営しています。

廣瀬さん それと、「irodori」のフリースペース内に、自分の感情に合わせて本を選べる「感情図書館 hidamari」が2024年にオープンしました。駄菓子屋や公園に行くという選択肢を持っている子もいれば、選択肢にすらならない子もいるんですよね。そんな子たちに「本で寄り添うことはできないか」と考えました。本が子どもたちの居場所になる可能性があるのでは、と感じたんです。
本は一般的に名前順に並んでいますが、そうすると内容が分からないので、子どもたちは本を手に取る機会が減ってしまいます。そこで、“感情分類”ということを始めました。「こんな気持ちの時にこの本を取ってくれるといいな」という想いから、感情で本を分類しています。こういう場所を増やして、全国展開できないかと今試行錯誤しているところです。
子どもたちのために様々な事業を立ち上げ

――事業は他にもあるんですよね?
廣瀬さん 他には、公園で大学生のお兄さんお姉さんが遊んでくれる「パークリーダー」事業があります。最近は習い事をしている子も多いので、友だちはたくさんいても、遊び相手がいない子がいます。また、西新井では中学生が“根性焼き”をしたというような事件が起きて、治安の悪さもあるため、保護者が安心して子どもたちを遊びに行かせられないという現状もあります。
なので、子どたちが目いっぱい遊べるようにするために、15時から18時くらいまで(季節によって時間は変動)の3時間、大学生が思いっきり遊んでくれるという事業を始めました。西新井栄公園と綾瀬ハト公園で、週3~5回ほどやっています。

廣瀬さん あと、能登の震災がきっかけで始まった災害時緊急こども支援チーム「J-CST」という事業もあります。震災があった際、大人はピリピリしていて、子どもたちは遊びたいけど遊べなかったり不安やストレスを抱えたりという状況で居場所がないという課題から、移動式遊び場で子どもの居場所をつくる事業です。遊び道具を「プレイカー」に乗せて、震災が起こったら現地へ向かいます。
あともう1つが、墨田区でやっている「あそび大学」という事業です。墨田区の町工場で使わなくなった素材を提供していただき、それらを素材としてこどもたちが自由にあそべる遊び場を大学や地域の方や行政の方と連携してつくっています。
――いろんな事業が展開されていますが、新たな事業はどのように生まれていくんですか?
廣瀬さん 基本的には「CFA」代表の中山のやりたいことで始まります。その中で、誰かとの出会いがあると、また新たな事業が生まれるということが多いですね。

――中山さんは地域では有名だと思うんですけど、はるちゃんから見て中山さんはどういう存在ですか?
廣瀬さん とにかく“子どものため”しか考えてない人ですね、代表は。学童でも、保護者からの要望や地域の方からのご意見がたくさん来るんですけど、それは本当に“子どものためなのか”を考えて、違っていたら戦いに行くんですよね。結構、果敢に戦いに行っちゃうタイプです(笑)
でも、それくらい子どものためにこうあるべきだ、という想いを持っているからこそ共感者が増えて、今もこうやって事業の拡大ができているんだろうなと感じます。
――はるちゃんが中山さんと喧嘩したりぶつかったりした経験は今までにありますか?
廣瀬さん 喧嘩はないですけど、「昨日までと言ってることが全然変わってるじゃん!」というのはあります(笑)だけど、代表の中では今その時のその選択が最善だから、私は「分かりました」って言って仕事していますね。
大学時の復興支援活動から「CFA」へ

――はるちゃんは「CFA」に新卒で入社していますが、なんでこの仕事を選んだんですか?
廣瀬さん 私は元々建築関係の大学に通っていて、建物から子どもの成長に携わりたいという想いで活動していたんです。けれど、大学時代に東日本大震災の復興支援に携わる活動をしたことをキッカケに、建物を建てることよりも、町の文化や人との繋がりに対して大学生でも何かできないかということを試行錯誤するような取り組みに興味を持ちました。その後、子どもや人に直接関わりたいと思う中で、「CFA」に出会って入社しました。
――人に直接関わりたい、というところでなんで“子ども”だったんですか?
廣瀬さん 大学生同士でチームを組んで、私がチームリーダーをやっていたんですけど、周りの大学生メンバーを見ていても、「就活、ダルい」「課題もダルい」「バイトもダルい」「全てダルい」のように、なにか絶望感を持っていたり未来に対してワクワクしてないように見えたりすることがあって。

廣瀬さん でも、それってその人だけのせいなのかな、って考えた時に、もしかしたら小さい時の過ごし方が影響しているんじゃないかと考えて、研究を始めたんです。その中で、幼少期の過ごし方ってすごく価値があるなと思ったので、子どもに関わりたいなと思いましたね。
――今、ユースマネージャーとして大学生と関わっていますよね。それって大学生が主体となって取り組む事業をマネジメントする中で、その頃に感じていた課題意識と、今の大学生の姿を比べてどう感じてますか?
廣瀬さん 今、学生メンバーが、高校生を含めて年間で160から170人くらい所属して「CFA」の事業に関わってくれていて、これだけ多くの学生が興味を持ってくれていることはやっぱすごく嬉しいなと思っています。

廣瀬さん コロナの影響もあり、大学ではサークルがなくなったり、先生の働き方改革によって部活のあり方も変わってきたりする中で、「何に熱中したらいいかわからない」とか「何かやりたいと思ってるけどそれをどこにぶつけたらいいかわからない」とかという学生もうちに入ってきてくれるんですよね。
「何かに挑戦したい」という学生たちがいることを感じられるのはすごく嬉しいなと思いますし、想いを形にできる場を一緒に作っていきたいなと思います。子どもや社会のために、知恵や場を与えることは、自分ができることの1つなのかなと思っています。
学生たちに伴走、苦労の先に見える景色

――「CFA」学生チームの大学生たちと関わる中で、どういうところに1番やりがいを感じてますか?
廣瀬さん 新しい挑戦をしたりイベントをやり切ったりした時に感じますね。例えば、駄菓子屋「irodori」が西新井で開催した「夏祭り」では、地域にインパクトを与えようという想いで取り組んだイベントで、2日間で3,000人もの人たちが集まってくれました。
子どもたちは無料で参加できて自分の意思で来られるし、そして、手触り感のあるあたたかいお祭りをつくろう、ということを学生たちと一緒に考えました。

――すごいですね。
廣瀬さん でも、学生メンバーは毎年変わるので、うまくいかないこともたくさんあります。ぶつかったり、朝までミーティングしたり、学生たちが作業をしたいから「はるちゃん、今日も終電までいいですか?」と言われて私も終電まで帰れなかったり。
だけど、何かのために夢中になって「やり切れたね」と言ってみんなで打ち上げしている時は、「みんな、よく頑張ったな!」と思いますし、その時間を迎えられることはすごく嬉しいです。
――学生たちとやることだから、失敗も付きものですか?
廣瀬さん 今年は地域に向けたイベントを5回くらい開催してきたんですけど、やっぱりうまくいかなかったこともありました。今季集大成のイベント時に目標を達成できなかったり、場の雰囲気とかチームビルディングとかもうまくいかなかったことがあったりしたんですよね。

廣瀬さん イベント初日の夜にリーダーの子たちを全員集めて、「本当にこれでいいと思っている?」と問いかけたこともありました。諦めてほしくないし、うまくいかなくて悔しいって思う時にこそ、立ち止まることが大切だと思うので、話し合いましたね。
――青春ですね。
この活動が地域や子どもたちの未来を変える――学生たちと共有したい想い

――今後は自らの仕事のキャリアをどんな風に歩んでいきたいと考えているんですか?
廣瀬さん 私はあんまり遠くまで考えないタイプなんですが、30歳までは「CFA」で学生たちと一緒に挑戦していきたいなと思ってます。
元々は、子どもたちと直接触れ合って子どもたちのために働きたいと思ってたんですけど、今の学生チームの事業や災害時緊急こども支援チーム「J-CST」や「あそび大学」に携わっていて、地域や行政の方・様々な団体の方々と関わっていると、「これを続けていたら社会が変わるかも!おもしろい!」と思うようになってきたんです。
なので、今やっていることを、これからもやっていきたいという気持ちがあるかなと思っています。

――いいですね!地域で遊んでますね。どういう社会になってったらいいなっていう、はるちゃんのビジョンはありますか?
廣瀬さん 難しいこと聞きますね(笑)学生たちと一緒に活動している中で、「自分たちが全力で何かに取り組むことで、地域や目の前の子どもたちの未来が少しずつでも変わっていく――」という実感を、学生たちにももっと感じられるようになってほしいという気持ちはあります。
今はまだ「自分たちでそんなことできるわけない」と思うことは多いんですよね。それは、学校教育で「与えられた宿題をやる」ような時間を過ごしてきた影響があって、そのような傾向が強いと思うんです。だけど、「本当はそうじゃない」と思えるようなキッカケをこれからも作り続けたいです。
――素敵です。今日はありがとうございました。
Chance For All
ホームページ
https://www.chance-for-all.org/

登壇者=廣瀬陽香さん
聞き手=大島俊映(トネリライナーノーツ編集長)
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/oshima/
編集補佐=しまいしほみ(トネリライナーノーツ 編集者)
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/shimai/
撮影=山本陸(トネリライナーノーツ カメラマン)
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/riku/