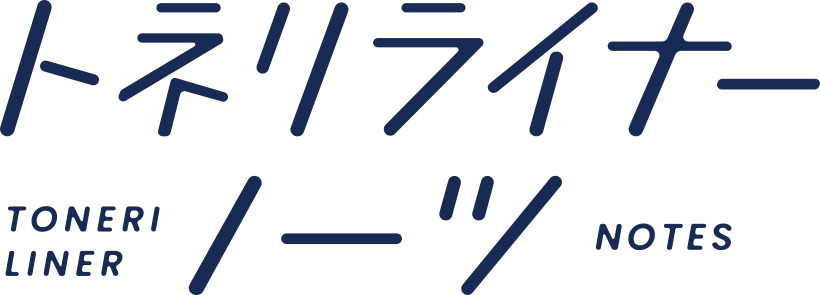トネリライナーノーツ編集長であり、日暮里舎人ライナー「舎人駅」より徒歩6分にある寺院「全學寺」副住職である大島俊映が、地域の中にある物語を、その物語の主役たちに代わって描く連載が「和尚代筆」です。
其の九では、「センジュ出版」代表の吉満明子さんの物語をお届けします。
(取材日:2024年7月2日)

個人的な話だけれど、「トネリライナーノーツ」編集長である私の“やらないことリスト”の中に、ライティングがある。自らの取材記事を作る際は、取材対象には自分で話を聞いて、ライティングは業務委託でお願いして、最後に再び自分で編集して、記事を完成させている。というか、ライティングは「やらない」というより、もう「できない」気がしているのだ。
それなのに、数年ぶりとなるライティングが、その道のプロフェッショナルである「センジュ出版」の吉満さんの取材記事になるなんて!取材をお願いしたあの時の酒場は、とても楽しかった。
「できない」ところはAIの力も借りて、でも、なるべく純度が高い吉満さんの物語を読者にお届けできたらと願う。
千住に根を下ろす、センジュ出版の創業

迷いに迷った末に、「センジュ出版という名前の由来から伺えますか?」という質問から、私は取材を始めた。取材の流れを考えた時に、吉満さんの物語に広がりが生まれると考えたからだ。吉満さんは「長く考えたわけでも、深い想いがあったわけでもないんです」と始めた。
社名のキッカケは、東日本大震災とご子息の出産だと言う。
震災があったあの日、吉満さんは八重洲の出版社で勤務中で、交通が麻痺した都内を、4時間半をかけて歩いて足立区の自宅まで帰った。「隅田川の橋を渡って荒川区から足立区に入ってくると、町の人たちが声をかけ合っていて。その光景を見た時に、私はこの地域に何年も住んでいたのに、そういう関係性が自分にはなかったことに気付いたんです」―遠くの親戚より近くの他人―。もし次にまたこんなことが起きたら、地域との繋がりを持っていなければ生きていけないかもしれない。そんな危機感を覚えた瞬間だった。

そして、その翌年に、吉満さんにご子息が誕生する。子どもが生まれると、「家族」の単位が「地域」に向かって自然と開いていった。その時に、「この子が育っていくこの場所に、私ができることを残したい」と強く思ったそう。
「だから社名に“センジュ”って入れたんです。土地への感謝の気持ちでもあるし、ここから出会う人とのつながりが広がっていけばという願いもあって。漢字の“千住”ではなく、カタカナの“センジュ”にしたのは、土地の名前だけに縛られない広がりを持たせたかったから。地名というより、この町を通じて出会う人たちとの関係性を表したかったんです」
コミュニティを編集、人の持つ引力を実感

「センジュ出版という名前を掲げて、実際に地域での活動が始まってから、想いに近づいてきた実感はありますか?」と私が尋ねると、「それは周りの方が決めること。でも、嬉しい出来事はたくさんありました」と答えてくれた。
例えば、センジュ出版が企画・開催するイベントや間借りスナックなどをキッカケに、他県から足立区を訪れる人が増えたこと。さらには、町に移り住んでくれた人までいると言う。「大それた町づくりはできないけれど、千住を面白がってくれる人が増えているのは、目の前で見ていて実感しています」

コミュニティをつくる。そう口で言うのは簡単だけれど、実際には「コミュニティになるかどうかは、人によって自然と決まっていくこと」だと、吉満さんは言う。その上で、「せめて、キッカケになる場を開いておきたい」と。
そして、吉満さんがこれまでのコミュニティ活動を通じて最も感じたことは何かを聞いてみると、こんな答えが返ってきた。「結局、人が人を呼ぶんですよ。場所がどれだけよくても、やっぱり“あの人に会いたい”って思えるかどうかで人は動く。私もそうですけど。私のまわりの人が、また誰かを連れてきてくれる。人の引力って、すごいなって思うんです」
吉満さんが向き合う“本”の正体

吉満さんは本づくりを生業としながらも、コミュニティづくりにも真摯に向き合っている。そんな彼女に、「本を編集することと、場を編集することの違いって何ですか?」と聞いてみた。
「場やコミュニティは“未完”のもの。つくったら終わりではなく、来る人や関わる人によって変化し続けます。でも、本は印刷された時点で“完結”するんです。もちろん、読む人によって解釈は違いますし、広がっていくものでもあります。でも、ページを増やしたり削ったりはできない。だからこそ、印刷前の段階で、今出せる最善を注ぎ込みます」
この話を聞いて、「本は“生む”もので、コミュニティは“育てる”ものなんですね」と伝えると、「まさに、そうですね」と吉満さんは頷いてくれた。

本の話が出たこのタイミングで、私は最も聞きたかった質問をした。「吉満さんにとって、“本”とはなんですか?」
「小さい頃は『モモ』(ミヒャエル・エンデ著)を読んで本を好きになって、学生時代は“活字に関わる仕事がしたい”と思って、社会人になってからは“編集者になりたい”と。段階的に気持ちは変化してきました」吉満さんは、言葉を選びながら答えていく。
現在は「センジュ出版」という会社の経営者であり、編集者でもある立場。その中で、吉満さんが今思う「本」とは、「紙に言葉で記された“非言語の情報”が詰まったメディア」だと言う。
「動画や音声と違って、言葉だけだからこそ“余白”がある。その“余白”に、読み手が想像を差し込むことができる。それが本の魅力だと思っています」
センジュ出版を10年続けられた理由

そんな吉満さんが本を書くのをお願いするキッカケは、その人の「声」だと言う。その人がどのようなパーソナリティを持っているかよりも、声色や話す時のリズム。“直感”を大切にしている。
その“直感”のことを、吉満さんは「肚」に聞くと表現する。頭や心ではなく、「肚」で決める。論理的に矛盾があったとしても、「肚」が今じゃないと言えば、やらない。
例えば、「センジュ出版を辞めたいと思ったことは何度もある」と、吉満さんは語ります。出版業は後払いの慣習でお金の流れも厳しいし、利益も出にくい。理性的に考えれば撤退してもおかしくない状況が、何度も訪れたそう。「財務の人からも辞めてもいいんですよって言われました。でも、その度に肚に聞くと、“今じゃない”って返ってくるんです」

「センジュ出版」を10年以上続けられている理由を掘り下げていくと、東北の方言にある「〜ささる(させられるように自然と動いてしまう)」という言葉を挙げてくれました。「食べささる、走らささる、みたいな。“自分でやっているんだけど、なんかやらされてる”みたいな感覚。センジュ出版は、私にとって“ささる”存在なんです」
「センジュ出版」を象徴する言葉である「しずけさとユーモア」についても最後に伺いました。「しずけさっていうのは、自分の小さな声を聞くための時間。編集もそうです。でも、私はスナックで歌ったり踊ったり、酒場で冗談を言ったりもする。だからユーモアも大事。最近は、しずけさは“この世とあの世をつなぐもの”、ユーモアは“この世からあの世へのお土産”なんじゃないかって思っています」
しずけさとユーモアの“あわい(間)”を行き来しながら、吉満さんはこれからも“ささる”ままに「センジュ出版」を続けていくのだろう。
センジュ出版
https://senju-pub.com/

取材=大島俊映(トネリライナーノーツ 編集長)
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/oshima/
撮影=山本陸
トネリライナーノーツ記事
https://tonerilinernotes.com/tag/riku/